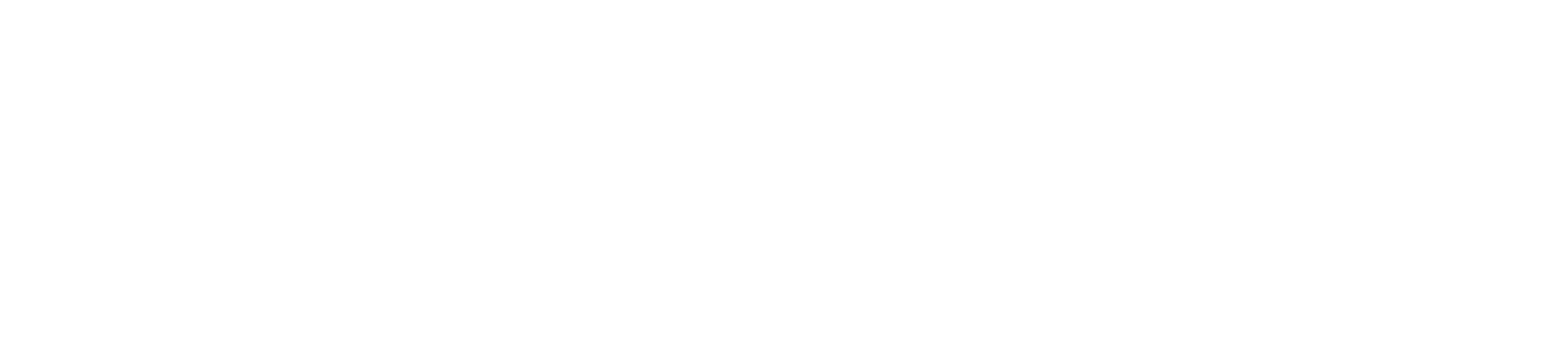概要 / Overview
高いコストパフォーマンスを誇り、安くて美味しいワインの定番として根付いている。19世紀の欧州では害虫(フィロキセラ)が発生し大きな被害をもたらした。他方、チリのブドウはフィロキセラの発生前に輸入されていた為、フィロキセラの害が無く無農薬でワインが造られている。最大品種はカベルネ・ソーヴィニョン。チリのカベルネ・ソーヴィニヨンを縮めた “チリカベ” はタンニン柔らかく口当たりが良いので日本で人気を博した。
プロフィール / Profile

豊かな自然と文化/ Rich Nature and Culture
チリは「3Wの国」と言われる。素晴らしい天候(Weather)、コロンビア、コスタリカと並び “南米3C”と称される美しい女性(Women)、美味しいブドウ酒(Wine)からの3つのW。
日本とチリ間で2007年に発効された経済連携協定に基づく関税率の逓減の恩恵で、日本のワイン国別輸入量でチリは第一位。関税メリットの具体例として、ボトル1本(CIF価格500円の場合)につき63円の差があり、日本の港に着いた時点でチリワインには63円のアドバンテージが生まれる。高額ワインに原価63円の違いは大したことはないが、スーパーやコンビニで販売されている低価格ワインには影響大である。
チリワインの優位性は関税に留まらない。ブドウ栽培にうってつけの自然環境に恵まれている。南アメリカ大陸の西海岸にあり、南端はパタゴニアの南氷洋、北端はアタカマ砂漠で南北の隔たりは4,300kmに及ぶ。他方で、国土の東西は狭く、最狭エリアは90km、最広でも380kmしかない。
ブドウ栽培地域は国土の中間部分(1,400km)に広がっている。中央部ではブドウはもとより様々な果樹栽培が盛んで、米国大手食品企業の果汁工場がパンアメリカン・ハイウェイに沿って軒を連ねている。
隣国アルゼンチンとの国境は6,000km級の山々が連なるアンデス山脈。銅など豊かな鉱物資源がチリ経済を支えてきた。南氷洋から北に向かって流れるフンボルト海流は冷たい海流で真夏でも海水浴が出来ないものの、沢山の漁場に恵まれており、サーモンなどチリ産の魚介類は日本のスーパーの魚売り場の定番になっている。
歴史 / History

鉱山富豪がワイン産業のスポンサー / Mining Industry Support Wine
ブドウ栽培は16世紀半ば、スペインのカトリック伝道者がワインを造るため “パイス種” を植えたことに始まる。1818年にスペインから独立したチリは、銅・銀・硝石などの鉱山資源をもとに経済成長を遂げると同時に、鉱山富豪が続々と誕生し、彼らがワイン産業のスポンサーになってきた。19世紀後半にはブドウの苗木だけでなく、栽培・醸造技術者もフランスから招聘し、本格的なワイン造りを始めている。当時の鉱山富豪はワインや醸造機器はもとより豪勢なシャトーやゲストハウスまで気に入ったものはすべて輸入した。現在、大手ワイナリーがホテルやオフィスとして使用している建物の建築様式や家具調度は当時のフランスそのもの。まさに鉱山が生み出したバブル時代を彷彿とさせる。
19世紀末にはフィロキセラに喘ぐヨーロッパのワイン生産地から、醸造家や栽培家がフィロキセラの被害がないチリに続々と移住してきた。彼らの作ったワインをワインが枯渇し始めたヨーロッパに向けて輸出。1889年のパリ万国博覧会でチリワインの品質は大いに評判となった。
生産過剰から復興へ / Recovery after Overproduction
20世紀に入るとヨーロッパのワイン生産が徐々に復興し、チリワインを必要としなくなった。消費不振で生産過剰に陥ったブドウ産業は新植禁止という事態になる。1960年代後半から1980年初めに至るまでチリのブドウ産業は深刻な生産過剰問題を抱え、ブドウ価格は殆どただ同然になってしまい、ブドウ栽培から離れる人が多かった。
そのような状況下、1979年にスペイン・カタルーニャのミゲル・トーレスがステンレス・タンクやオーク樽などの新しい醸造技術を設置し、フレッシュでフルーティーなワインを造りながら少しづつ前進した。その後、農業物の価格引き上げ策が功を奏し、1980年代半ばになってようやくワイン産業に活気が戻る。そのような経緯から、チリワインは最も遅く国際市場に参入したのである。
適地適品種 / Suitable Variety for Suitable Area
1990年に入ると先駆け生産者の成功を目の当たりにした人達が次々とワイン造りに新規参入してきた。これには、それまでワイナリーにブドウを販売していた栽培者が自前でワインを造るようになったケースと、新しく土地を買いブドウを植えた新規参入の2通りがあった。
チリワイン産業は21世紀を目前にし、新しいステージを創造しなければ国際市場で生き残ることが出来ないという課題に直面していた。 “ジャムのようなヴァラエタルワイン” と言われる品質からプレミアムワイン造りへと舵を切ったのである。チリワインの新しいステージはテロワールをコンセプトにしたワイン造りをすることだった。
テロワールが土・気候・人為という3つの要素で構成されるとするならば、チリはそれらを明確に意識してブドウ畑の選定と耕作に取り組んだ。その一例として、海外近くのカサブランカ・ヴァレーは絶対量の不足していたシャルドネの生産適地を冷涼地に求めている。
チリは平凡なヴァラエタルワインから脱却し、新鮮な果実味と複雑味を備えたワイン造りを目指して、各生産者は先を競って最適な傾斜地を探し、涼しい風の吹きこむ土地を見つけてブドウ樹を植えた。それらの樹が最良の樹齢に達し、高いクオリティーのワインを生み出している。
気候風土 / Climate & Terroir

細長い国 / Long & Narrow Country
チリは南北に細長い国で、東側をアンデス山脈、太平洋側に海岸山脈が走り、二つの山脈の中間部セントラル・ヴァレーが広い平地になっている。冬の数カ月だけ集中して雨が降り、晩春から夏の終わりまで乾燥する典型的な地中海性気候。
セントラル・ヴァレーは冬に雨が降るだけなので、灌漑用水が欠かせない。従って、耕作地は河川の流域に限られる。
チリの河川はアンデスから太平洋に向かって流れており、流路の短い急流が何本も走る。アンデス川山脈の東側を流れる大河アマゾンやラプラタとは対照的に、チリの多くの河川は夏になると干上がってしまい、川床が剝き出しになる。
伝統的な灌漑方法 / Traditional Irrigation
それぞれの耕作地には古くからアンデス山脈の雪解け水を引き込むための灌漑用水がある。チリの伝統的な灌漑の仕方は、雪解け水を貯めて耕作地に流すスタイル。水がほとんど来ないカサブランカ・ヴァレーでは、井戸を掘って水を確保し、ドリップ・イリゲーション(点滴灌漑)で水の消費を防いでいる。
ブドウ成熟期の冷涼な気候 / Cool Climate when Grape Ripening Period
他の重要な要素は、冷気(ブドウ成熟期の涼しさ)にある。南半球のブドウ栽培地は、北半球のに比べて緯度の低いところに位置する。これは、寒さや雨による栽培リスクを避ける為のエリアを選定・開拓した背景から。緯度が低いと日射角が鋭くなり日照量が多くなる。ブドウは強い紫外線に抵抗して果皮を暑くし、その果皮にはポリフェノールが豊富に含まれる。だから、チリワインは冷涼地のブドウ(ピノ・ノワールやシラー)で造ったものでも色が濃いものが多い。
さて、その涼しさはどこから来るのか。一つは万年雪を被っているアンデス山脈から吹き下ろす風、もう一つは太平洋を流れるフンボルト海流。
近年はクール・クライメイト(冷涼な栽培環境)の枠を超え、これ以上の条件ではブドウ栽培が出来ない究極の栽培環境(エクストリーム・アルティメイト・クライメイト)を求める栽培家が増えている。
土地の特徴 / Terroir
地質学的に見ると、今から約1億年前にナスカ・プレートが南米プレートにぶつかってその下に滑り込み、その衝撃でアンデス山脈が形成された。海岸山脈はアンデスの山々より低い丘陵であり、アンデス形成以前の海岸山脈は幾つかの島であり、現在のチリの国土は水面下にあったと考えられている。
セントラルヴァレーは2つのプレートの衝突で隆起し陸地になり、そこにアンデスの造山活動で降ってきた火山岩や灰が堆積し、河川が運んだ砂利や粘土が層を成し出来上がった。
海岸山脈はアンデスのように南北に綺麗に連なった山々ではなく、隆起、陥没を繰り返しながら伸び縮みし、川に浸食されて混沌とした無秩序な形になっている。そういう成り立ちから、アンデスの麓は主に火山性土壌や崩積土、中央部の平地は肥沃な沖積土、海岸山脈側は砂が多く、痩せた土壌で石灰質土壌が支配的。
フィロキセラの被害なし / Phylloxera-free Area

ブドウの生育期間(発芽から収穫まで)は乾燥が続くので、ボトリティスやべト病などの菌類の病気に罹らないことがチリにおけるブドウ栽培の特徴。また、フィロキセラの被害がないので接木する必要がない。
ナチュラル灌漑からドリップ・イリゲーション(点滴灌漑)に切り替えると、フィロキセラの危険性が高まると言われている。よって、チリではフィロキセラの棲息が確認された場合に備え、接木で新植する畑が増えている。
農業省農牧庁(SAG)の植物検疫は非常に厳しく、新品種を外国から輸入する際には数年かけてウイルス・チェックすることを義務付けられている。チリにフィロキセラの被害がないのは「東をアンデス、西を太平洋、北をアタカマ砂漠、南に南氷洋、に囲まれる自然の要塞でフィロキセラを寄せ付けない」という地理的特徴に起因する。
主なブドウ品種 / Grape Variety

ボルドー品種が多い / Many Bordeaux Varieties
カベルネ・ソーヴィニョンが全体の3割(マイポ・ヴァレーが主産地)を占め、次いでソーヴィニョン・ブラン、メルローが続く。以下、チリにおいて特徴ある品種
「カルメネール」
19世紀にボルドーから持ち込まれた品種。熟期がとても遅く、受粉の時期に低温になると花震いを起こすことからボルドーでは栽培が途絶えてしまった品種であるが、天候の良いチリでは生き続けている。チリでは長らくメルロだと勘違いされていた(1994年にようやく認定)。カルメネールの特徴は色素の濃さにある。語源の Carmine は “深紅色” の意味。熟した果実と樽熟成でコーヒーやチョコレートのような香りを持つ。口に含んだ時の味わいは、柔らかくて丸いタンニンと凝縮した果実味が感じられる
「パイス」
チリのブドウ畑はパイスと共に歩んできた。樹齢が古くなり自然に収穫が落ちて品質が向上している。また、野生化したパイスを収穫してワインを造る動きがある。ブドウ樹はブドウ科の性落葉植物。人間がブドウを栽培するようになり、特定の仕立て方と剪定方法から現在のブドウ畑が出現したが、剪定せず天然のままにしておけば、ぶどう樹は蔓を伸ばし、灌木に寄り添って日の当たるところで実を結ぶ。マウレの海岸山脈の中に放置されていたパイスが野生化し、水場近くの灌木に実をつけており、樹に梯子をかけて収穫している
「カリニャン」
“VIGNO” ラベルの表示で注目を浴びている。VINGOの製造基準はマウレ・ヴァレーのカリニャンを65%以上使用したワインであること、樹齢30根年以上、灌漑をしていない、特定容器で24ヶ月以上熟成したことが条件。1939年イタタ・ヴァレーの大地震で、カウケネスのブドウ畑のパイスが壊滅した。パイスに変わる新品種がフランスが導入・新植されたのが、ラングドックのカリニャンであった。
【ワイン法と品質分類】
チリでのワインは、①ヴィティス・ヴィニフェラのブドウ果汁を発酵させたもの、②ワインの製造工程でアルコール、蔗糖などの糖類、人エ甘味料を使用してはならない、③ワインはブドウ果汁の糖分だけで造らなければならない、④アルコール分は11.5%以上でなければならない、と定義されている。チリの原産地呼称 D.O.ワインにはフランスの A.O.C. のような収穫量の制限や栽培品種の特定、熟成期間などの醸造法等に関する規制がない。
「義務付けられているラベル表示の項目」
①ワインの種類(赤・白ワインなど)、②製造者(瓶詰者)名と所在地、③ワインの容量、④アルコール含有量、⑤ “Produce of Chile” など、原産国がチリであることが分かる記載、⑥ワインの原産地呼称 D.O(当該産地のブドウを75%以上使用)、⑦ブドウ品種名(当該品種が75%以上使用されているもの。2品種もしくは3品種をアッサンプラージュした場合、いずれの品種も15%以上使用し、使用比率の多い順に左から右に並べて表示可能)、⑧ワインの収穫年(当該生産年のワインを75%以上使用のこと)
【ワインの産地と特徴】
ブドウ栽培地域は北部、中央部、南部の3つに分けられる。 その長さは1.400kmにも及び気候条件や土壌に大きな違いがある
「セントラル・ヴァレー」
広大なブドウ産地。チリのブドウ栽培はここで始まった。伝統的にはボルドー品種とパイスが栽培されてきたが、最近はテロワールの特徴に合わせた新品種の栽培が盛ん。雨量は年間300mm未満と極端に少なく、耕作には灌漑が必要。各州の原産地呼称として、マイポ・ヴァレー(首都州)、ラペル・ヴァレー、カチャポアル・ヴァレー、コルチャグア・ヴァレー、クリコ・ヴァレー、マウレヴァレー(チリ最大のブドウ産地)がある。
「サウス」
イタタ・ヴァレー、ビオビオ・ヴァレー、マジェコ・ヴァレーという3つのサブリージョンで構成される。降水量が多く灌漑を殆ど必要としない。パイスの栽培が多くワインの殆どが国内消費用に向けられている。
「アウストラル」
2011年に新しく認定された原産地呼称で、南に位置するためアウストラル(南極)から名付けられた。チロエ島にアルバリーニョが植栽されており、ここがチリ最南端のブドウ畑である。
【新しい原産地呼称表示の採用】
チリの原産地呼称は北から南に向かって国土を行政区分(州)に沿って水平に切っている。しかし、国を北から南に向かって州毎に産地を区分しても、ブドウとワインの特徴が掴めないことが、ブドウ畑の開拓とテロワールから分かってきた。
例えば、リマリ・ヴァレーとビオビオ・ヴァレーは1,000km以上離れているが、栽培品種は共通項が多い。他方で、東西にわずか50kmしか離れていないマイポ・ヴァレーとカサブランカ・ヴァレーでは栽培品種やワインが大きく異なる。それらを考慮し、2011年に従来の原産地呼称表記に付記する格好で、二次的な産地表示が出来るようになった。①コスタ(海岸に面した畑)、②エントレ・コルディリェラス(海岸山脈とアンデス山脈の間、つまり中央部の平地)、③アンデス(アンデス山脈側の斜面)
「コスタ」
チリの海岸線は南北4,000kmを超える。その海岸は南極海からフンボルト寒流が流れ、海水は真夏でも冷たく、人々は砂浜で日光浴はするが海水浴は水温が低すぎて出来ない。この冷たい海から内陸に向かって吹く海風がブドウ畑に及ぼす影響はきわめて大きい。
コスタは、チリワインに多様な広がりをもたらしたと同時に、新しいスタイルをチリワインに提供している。土壌にカルシウムなど海洋性の要素を多く含んでいるのが特徴。コスタのブドウから生まれるワインには、ミネラルや塩味が強く感じられ、心地よいシャープな酸味を伴っている。
「エントレ・コルディリェラス」
コルディリェラは山のことで、エントレ・コルディリェラスは “2つの山脈の間” という意味。アンデス山脈と海岸山脈の間に位置する平坦で肥沃な地域を指している。ボルドーのアントル・ドゥー・メール(2つの大河に挟まれた平坦な地域)に似た呼称である。
チリの農業はエントレ・コルディリェラスで始まった。地中海性気候で肥沃な沖積土壌に恵まれたこの地域は、ブドウ栽培のみならず小麦や果樹などチリ農業を支える中心的な耕作地。エントレ・コルディリェラスのブドウはチリワイン生産の約60%を占めている。
「アンデス」
チリとアンデス山脈は一体不可分の関係にあり、アンデスの山々がチリの国土に及ぼす気象上の影響はきわめて大きい。例えば、早朝にアンデス山中で形成された冷気の塊が、朝日とともに山間から麓へと吹き下ろす。山の麓に拓かれたブドウ畑はそのお陰で涼しく風通しもよい。更には遅霜の降りる心配もない。日中は強い日差しを受ける斜面は日が落ちると急激に冷えるので昼夜の気温差が大きくなる。こういう理屈を昔の人々は知っていて開拓当初からアンデスの麓にブドウ畑が拓かれた。雪解け水を使えば畑も簡単に灌漑出来た。
アンデスに位置するブドウ畑は、その標高や斜面の向いている方向、斜度などによってブドウに大きな違いが生まれるものの、凝縮した品質の高いブドウを生み出している。